『因果愛』
少し遅くなりましたが、私の最も信頼している大学生、井上太一君から素敵な文章を頂きました。
19歳でこのような文章、、、脱帽です。
『因果愛』
地域によってジャズの濃度に違いがあるという話はたびたび耳にする。
詳しくは知らないが、ジャズには核となる国や街があって、それらを中心として拡がっている。
要するに、ジャズには「本物」があるという話だ。
ものごと、殊に音楽におけるジャンルというものにオリジナルが存在するという話は非常にわかりやすい。ではオリジナルとは何か。
僕は大学のビッグバンドに所属しているのでとてもよくわかる。
僕らは日々、部室に集い原曲を聴き、原曲の楽譜を読み込み、演奏している。つまるところ
オリジナルとは原曲だ。
果たして、本当にそうだろうか?
「こんな音楽聴いたことない。初めて聴く音だ。」
ニコライ・ヘス トリオの演奏を聴いて、思ったのはそれだ。
たしかに、これは何の音楽ですかと尋ねてヨーロッパのジャズですと言われると、うなずける。
しかしやはり、圧倒的にオリジナルだと感じた。
そもそも、ヨーロッパのジャズというものの概念が自由すぎる。
まず、アメリカのジャズとは本質的に違うように感じる。
僕の知る限りにおいては、ただその音楽家の暮らす地域や、その音楽の生まれた土地がたまたま
ヨーロッパであったというだけで、そこで生み出されるジャズは、すべてオリジナルであるという印象がある。それらの音楽は、俺は俺の音、俺の音楽を奏でるのだという熱意が原点にあって、それがたまたま
ジャズという文脈の中に芽吹く因果にあったのだ。
そして、ニコライ・ヘスの音は、その「たまたま」を深く愛していた。
と書いて、ハッとした。先にヨーロッパのジャズについて書いた「アメリカのジャズとは本質的に違うよう
に感じる」というのは誤りである。
かつてアメリカに生まれたジャズという音楽は、それこそ自らの因果を想い、愛し、憎み、それでもなお
愛し、祈った音楽ではなかっただろうか。
すると、なぜ僕は「アメリカのジャズとは本質的に違うと感じる」と書いてしまったのか。
僕たちは「原曲を聖典とし、それらを復唱することで演奏を行うと述べた。
もちろん、原曲に敬意を払うということが、今のジャズ演奏の土台であることは確かだと思う。
しかし往々にして因果、「なぜ、僕たちはこの音楽を奏でるのか」もとい「なぜ僕たちはここにいるのか」ということについての思想は、ないがしろにされている。
なるほど、ヨーロッパのジャズは、僕らの演奏するアメリカのジャズと違っていたわけだ。
では、僕たちのジャズは模倣に終わるしかないのかというと、否だと思う。
僕たちにだってオリジナルはできる。僕たちには、僕たちの因果がある。
僕たちは今、ここに生きて、生活している。
もちろん、演奏技術如何は、圧倒的にある。
しかしそれ以上に、やはり僕はニコライ・ヘス トリオのその因果愛に魅せつけられた。
ジャズとは、私は私であるということを詠う音楽であるということを見せつけられた。
僕はあの日、ニコライ・ヘスという人の暮らし、イェンス・スコウ・オルセンという人の息づかい
池長一美という人の矜持を、音に聴いたのだ。
だから今日、僕は街を歩く。人と話をする。ご飯を食べる。そうやって街に暮らす。
そして、ビッグバンドでドラムを叩く。
井上 太一 十九歳
長崎大学スウィングボートジャズオーケストラ五三代ドラムパート。
神戸に生まれ育ち十八になるも、何の因果か先祖眠る長崎に暮らし始めて早一年。
まさに水面に揺れる帆舟の如く、ゆらりゆらりと十代最後を過ごして居ります。



アマゾンは、こちら
http://www.amazon.co.jp/Rhapsody-Nikolaj-Hess-feat-Marilyn-Mazur-x/dp/B018ISK64K
19歳でこのような文章、、、脱帽です。
『因果愛』
地域によってジャズの濃度に違いがあるという話はたびたび耳にする。
詳しくは知らないが、ジャズには核となる国や街があって、それらを中心として拡がっている。
要するに、ジャズには「本物」があるという話だ。
ものごと、殊に音楽におけるジャンルというものにオリジナルが存在するという話は非常にわかりやすい。ではオリジナルとは何か。
僕は大学のビッグバンドに所属しているのでとてもよくわかる。
僕らは日々、部室に集い原曲を聴き、原曲の楽譜を読み込み、演奏している。つまるところ
オリジナルとは原曲だ。
果たして、本当にそうだろうか?
「こんな音楽聴いたことない。初めて聴く音だ。」
ニコライ・ヘス トリオの演奏を聴いて、思ったのはそれだ。
たしかに、これは何の音楽ですかと尋ねてヨーロッパのジャズですと言われると、うなずける。
しかしやはり、圧倒的にオリジナルだと感じた。
そもそも、ヨーロッパのジャズというものの概念が自由すぎる。
まず、アメリカのジャズとは本質的に違うように感じる。
僕の知る限りにおいては、ただその音楽家の暮らす地域や、その音楽の生まれた土地がたまたま
ヨーロッパであったというだけで、そこで生み出されるジャズは、すべてオリジナルであるという印象がある。それらの音楽は、俺は俺の音、俺の音楽を奏でるのだという熱意が原点にあって、それがたまたま
ジャズという文脈の中に芽吹く因果にあったのだ。
そして、ニコライ・ヘスの音は、その「たまたま」を深く愛していた。
と書いて、ハッとした。先にヨーロッパのジャズについて書いた「アメリカのジャズとは本質的に違うよう
に感じる」というのは誤りである。
かつてアメリカに生まれたジャズという音楽は、それこそ自らの因果を想い、愛し、憎み、それでもなお
愛し、祈った音楽ではなかっただろうか。
すると、なぜ僕は「アメリカのジャズとは本質的に違うと感じる」と書いてしまったのか。
僕たちは「原曲を聖典とし、それらを復唱することで演奏を行うと述べた。
もちろん、原曲に敬意を払うということが、今のジャズ演奏の土台であることは確かだと思う。
しかし往々にして因果、「なぜ、僕たちはこの音楽を奏でるのか」もとい「なぜ僕たちはここにいるのか」ということについての思想は、ないがしろにされている。
なるほど、ヨーロッパのジャズは、僕らの演奏するアメリカのジャズと違っていたわけだ。
では、僕たちのジャズは模倣に終わるしかないのかというと、否だと思う。
僕たちにだってオリジナルはできる。僕たちには、僕たちの因果がある。
僕たちは今、ここに生きて、生活している。
もちろん、演奏技術如何は、圧倒的にある。
しかしそれ以上に、やはり僕はニコライ・ヘス トリオのその因果愛に魅せつけられた。
ジャズとは、私は私であるということを詠う音楽であるということを見せつけられた。
僕はあの日、ニコライ・ヘスという人の暮らし、イェンス・スコウ・オルセンという人の息づかい
池長一美という人の矜持を、音に聴いたのだ。
だから今日、僕は街を歩く。人と話をする。ご飯を食べる。そうやって街に暮らす。
そして、ビッグバンドでドラムを叩く。
井上 太一 十九歳
長崎大学スウィングボートジャズオーケストラ五三代ドラムパート。
神戸に生まれ育ち十八になるも、何の因果か先祖眠る長崎に暮らし始めて早一年。
まさに水面に揺れる帆舟の如く、ゆらりゆらりと十代最後を過ごして居ります。



アマゾンは、こちら
http://www.amazon.co.jp/Rhapsody-Nikolaj-Hess-feat-Marilyn-Mazur-x/dp/B018ISK64K
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
カテゴリ
最近の記事
34th KOBE MODERN JAZZ CLUB (7/16)
マルコ ・ メスキーダ京都祇園 (6/24)
唯一の東京公演 (6/18)
初来日 (6/17)
復活します!! (10/1)
兵庫1区 もりやま まさひと (10/29)
海外と日本を繋ぐ その1 (4/11)
クリスマスプレゼントのお知らせ (12/6)
サヴォイ・カレー (8/26)
ヴォイスカレー (4/30)
過去記事
最近のコメント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード
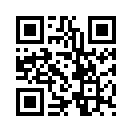
アクセスカウンタ
読者登録







