夜間工事
2月17日と18日、お店をお休みしてエアコンの入れ替えをします。
はい、このブログはその真っ最中に書いてます。
夜9時から朝の5時まで><の予定です。
今回の工事は、30年も頑張って働いてくれたエアコン君を入れ替えるのですが、昨今、水冷式エアコンってあんまりないんです><、さらに冷暖房の切り替えとなると、トホホ。
冷房設備だけならインドに輸出する物があるそうですが、日本って寒いじゃないですか><。
暖房は別途、組み込み式の特注しかないんですって、グハ〜!!
あんまり暇な私は、こんなんを見てます!!
なんで???演奏時間が長いから工事で一人っきりだから声が聞きたい!!ってダケです。
さあ、工事のお話。
30年も使ってると配水管、バルブ、排水管など全部、汚れてたり薄くなってたり劣化してますよね。動脈硬化みたいに。それを作り換える。
さらに30年前の企画のエアコンがそのまま入る訳もなく、ダクトやなんやらを現場加工ですよ〜〜。
でも、業者さん『よく保ちましたね!!!』って言ってくれました!!確かにちゃんと掃除したりしてたからね。
これが最高のエコだと思うんだけど。
そういえば、お店のアンプやオーディオも古いなあ!!
少し、お店のスピーカーについて
うちで使ってるスピーカーは、ALTEC 604-B です。

どんなんか?って言うと
アルテック604シリーズの原型となる最初の同軸型スピーカー「601」の発表が1943年。
12 インチの601同軸型スピーカーは多くの有名なアルテック・ランシングのデュプレックス同軸スピーカーの最初の製品となりました。
601同軸型スピーカーは米国海軍に対空砲火訓練システムとして搭載されたとあります。
1945年、世界中で最も著名で、最もプロの現場での実績を上げる同軸型スピーカー604シリーズの初代が登場します。元々、潜水艦のソナー用のスピーカーユニットとして開発され、1944年には完成しましたが、第二次世界大戦には間に合わなかったとあります。
低域、高域それぞれ独立したマグネットを使用し、ウーファーの中を貫通したホーンから高域を放射するという非常に贅沢な、ある意味理想的な構造。幅広い周波数のカバーと、ダイナミックレンジ、そしてなによりもこの方式の最大のメリット、点音源による群を抜く定位感がその後の絶大なる信頼感の源となったことは改めて言うまでもありません。そして、アルテックはこの独自の同軸構造のユニットを「デュプレックス」シリーズと総称していました。
特に駆動するアンプが真空管からトランジスターへと変化するのに合わせたインピーダンスの16Ωから8Ωへの変更、フィックストエッジからフリーエッジへの改良による耐入力の向上、アルニコの最終期においてはタンジェンシャルフェーズプラグを導入し、ハイエンドの伸びを一気に加速し、また、長年その顔となっていたセクトラルホーンを定指向性のマンタレーホーンへ変更、ここでレンジの拡大と透明感を付加された音に、その後世界的コバルトの高騰からアルニコからフェライトへのマグネットの変更などが大きなトピックスとなりました。
もっともその主たるはレコーディングスタジオあるいは映像関連のモニターユースと言うのは周知の通りですが、1973年のビルボード誌調査においてはアルテックランシングのスピーカーシステムは「レコーディングスタジオ」で他を圧倒し一番多く使われているという結果が発表されたりしました。
モニタースピーカーといいますと検聴用、検証用ひいてはあら探し用などとネガティブなイメージもあるかもしれませんが、このアルテックの名機604シリーズに関してはプラスしてその音楽性の豊かさ、「楽器の音」がするとしてミュージシャンや、特に耳が良いとされる日本のオーディオファイルを中心としてプロユース以外にも絶大な人気を誇りました。
オールド、ヴィンテージファンの中では昔の604が最高だと言う方が沢山いらっしゃいます。実際現在でも初代からB,C,Dはかなり高額で取引されていますし、その豊潤でコクのあるアルテックトーンはシンプルで高品位な真空管アンプでこそ活かされるとされています。また実際のスタジオユースにおいてはE~Gが全盛期だったと思われます。
てな具合で古〜〜なんです。しかし、暇だ。この工事。
村田
はい、このブログはその真っ最中に書いてます。
夜9時から朝の5時まで><の予定です。
今回の工事は、30年も頑張って働いてくれたエアコン君を入れ替えるのですが、昨今、水冷式エアコンってあんまりないんです><、さらに冷暖房の切り替えとなると、トホホ。
冷房設備だけならインドに輸出する物があるそうですが、日本って寒いじゃないですか><。
暖房は別途、組み込み式の特注しかないんですって、グハ〜!!
あんまり暇な私は、こんなんを見てます!!
なんで???演奏時間が長いから工事で一人っきりだから声が聞きたい!!ってダケです。
さあ、工事のお話。
30年も使ってると配水管、バルブ、排水管など全部、汚れてたり薄くなってたり劣化してますよね。動脈硬化みたいに。それを作り換える。
さらに30年前の企画のエアコンがそのまま入る訳もなく、ダクトやなんやらを現場加工ですよ〜〜。
でも、業者さん『よく保ちましたね!!!』って言ってくれました!!確かにちゃんと掃除したりしてたからね。
これが最高のエコだと思うんだけど。
そういえば、お店のアンプやオーディオも古いなあ!!
少し、お店のスピーカーについて
うちで使ってるスピーカーは、ALTEC 604-B です。

どんなんか?って言うと
アルテック604シリーズの原型となる最初の同軸型スピーカー「601」の発表が1943年。
12 インチの601同軸型スピーカーは多くの有名なアルテック・ランシングのデュプレックス同軸スピーカーの最初の製品となりました。
601同軸型スピーカーは米国海軍に対空砲火訓練システムとして搭載されたとあります。
1945年、世界中で最も著名で、最もプロの現場での実績を上げる同軸型スピーカー604シリーズの初代が登場します。元々、潜水艦のソナー用のスピーカーユニットとして開発され、1944年には完成しましたが、第二次世界大戦には間に合わなかったとあります。
低域、高域それぞれ独立したマグネットを使用し、ウーファーの中を貫通したホーンから高域を放射するという非常に贅沢な、ある意味理想的な構造。幅広い周波数のカバーと、ダイナミックレンジ、そしてなによりもこの方式の最大のメリット、点音源による群を抜く定位感がその後の絶大なる信頼感の源となったことは改めて言うまでもありません。そして、アルテックはこの独自の同軸構造のユニットを「デュプレックス」シリーズと総称していました。
特に駆動するアンプが真空管からトランジスターへと変化するのに合わせたインピーダンスの16Ωから8Ωへの変更、フィックストエッジからフリーエッジへの改良による耐入力の向上、アルニコの最終期においてはタンジェンシャルフェーズプラグを導入し、ハイエンドの伸びを一気に加速し、また、長年その顔となっていたセクトラルホーンを定指向性のマンタレーホーンへ変更、ここでレンジの拡大と透明感を付加された音に、その後世界的コバルトの高騰からアルニコからフェライトへのマグネットの変更などが大きなトピックスとなりました。
もっともその主たるはレコーディングスタジオあるいは映像関連のモニターユースと言うのは周知の通りですが、1973年のビルボード誌調査においてはアルテックランシングのスピーカーシステムは「レコーディングスタジオ」で他を圧倒し一番多く使われているという結果が発表されたりしました。
モニタースピーカーといいますと検聴用、検証用ひいてはあら探し用などとネガティブなイメージもあるかもしれませんが、このアルテックの名機604シリーズに関してはプラスしてその音楽性の豊かさ、「楽器の音」がするとしてミュージシャンや、特に耳が良いとされる日本のオーディオファイルを中心としてプロユース以外にも絶大な人気を誇りました。
オールド、ヴィンテージファンの中では昔の604が最高だと言う方が沢山いらっしゃいます。実際現在でも初代からB,C,Dはかなり高額で取引されていますし、その豊潤でコクのあるアルテックトーンはシンプルで高品位な真空管アンプでこそ活かされるとされています。また実際のスタジオユースにおいてはE~Gが全盛期だったと思われます。
てな具合で古〜〜なんです。しかし、暇だ。この工事。
村田
Posted by クレフ at 2013年02月18日 23:58
その他
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
カテゴリ
最近の記事
34th KOBE MODERN JAZZ CLUB (7/16)
マルコ ・ メスキーダ京都祇園 (6/24)
唯一の東京公演 (6/18)
初来日 (6/17)
復活します!! (10/1)
兵庫1区 もりやま まさひと (10/29)
海外と日本を繋ぐ その1 (4/11)
クリスマスプレゼントのお知らせ (12/6)
サヴォイ・カレー (8/26)
ヴォイスカレー (4/30)
過去記事
最近のコメント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード
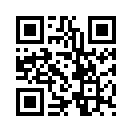
アクセスカウンタ
読者登録







